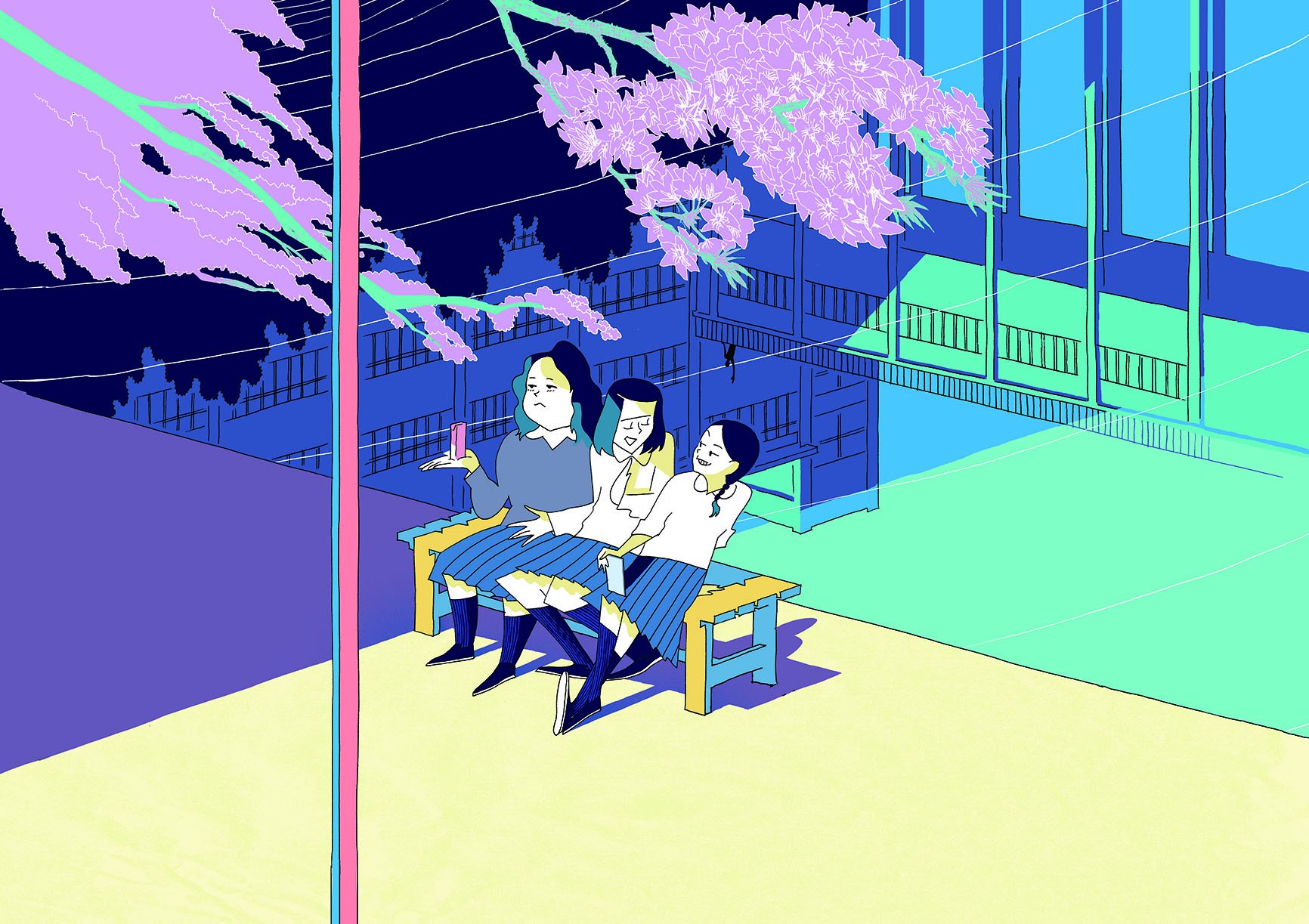ブログのフォーマットをはてなブログ に変えてみました。しゅんです。
2014年からはじめて三年目になる個人的ベストカルチャー。遅くなってしまったけど2016年をまとめてみます。まずは長ったらしい前置きを。
2016年のいくつかのトピック、ピッチフォークの年間ベストアルバム1位から5位までがすべてビルボード で1位を獲得したものであったこと(4位のボウイ以外は黒人ミュージシャン)、『この世界の片隅に 』がキネマ旬報 と映画芸術 の邦画ベスト1位に映画秘宝 の2位と主要映画誌のベストを独占したこと、ボブ・ディラン のノーベル文学賞 受賞、芥川賞 受賞作『コンビニ人間 』のヒット、『フリースタイルダンジョン 』を契機とした日本語ラップ ブームなどは、ある側面から切り取ればひとつの中心を共有した同心円である。その中心点とは一言で言うとこうなる。「ポピュリズム に対抗するポピュリズム 」と。
pitchfork.com
大衆社会 批判の嚆矢『大衆と反逆』で有名なオルテガ ・イ・ガセットは1925年に『芸術の非人間化』という文章(白水社 『オルテガ 著作集 第3巻』収録)の中で、当時諸ジャンルで台頭しつつあった新芸術の特徴を「非人間的」と形容している。それまでの19世紀ロマン主義 時代の芸術は感傷的な人間ドラマで人々の現実感覚と感情を刺激した。代表格がワーグナー やユゴー のような作家だ。対して、新芸術はそうした人間性 の押しつけを拒絶した。ドラマで感動を起こそうとするのは隣人の喜びや苦しみが感染しやすいという人間の弱みを利用しているにすぎない、この感染は精神的なものではなくタマネギを切れば涙が出るのと同じ機械的 な反射反応だ。芸術に精神性を与える為には、非人間的で非現実的かつ知的で美的な要素を持たなくてはいけない、芸術作品を芸術そのものとして客観性をもって「観照」できるような力を有しなくてはいけない。こうした意識を持った新たな作家がドビュッシー やマラルメ 、あるいはプルースト やピカソ のような作家である。オルテガ は以上のような定義付けを行ったのだ。ロマン主義 と新芸術の区分けは、大衆娯楽芸術とハイアートという分け方にに近いものとかなり重なるところがある。
VIDEO
VIDEO
二つの区分を同じ時代に並列するものではなく、時代の流れのなかで縦列しているものと見なしているところは興味深いが、オルテガ が分析した時代以降その区分けはより曖昧なものとなっているし、ある種使い古された、ステレオタイプな分け方である感は否めない。エリーティズム だと批判する声もあるだろう。だが、重要なのは作り手ではない鑑賞する側の態度にも二通りあることを示したことである。これは映画で考えるとわかりやすい。『タイタニック 』や『君の名は』を観てそこで展開される恋物語 に感情移入して涙を流す態度と、ゴダール やタルコフスキー の映画を前にして知性・感性をフル稼働させて観照する態度の差は明らかに今も存在している。
この二つの態度を、ここでは仮に前者を「感動派」、後者を「観照派」と名付けよう。
2016年の文化状況の特徴はこの二つの態度の距離が今までにないほど近づいたところにある。もちろん、作品の距離が近づいているせいもある。特に音楽に関しては先日グラミーを争ったアデル、ビヨンセ のアルバムをはじめポップフィールドで活躍するアーティストの作品の充実っぷりが顕著だった。だが、ロマン主義 と新芸術、あるいは大衆文化とハイアートの混合は今に始まったことではないし、ロックや映画といったここ100年で栄えた芸術フォームはジャンル自体がアマルガム 的である。ヒップホップやアニメーションならなおさらだ。接近の理由は作品そのもの以外に見いだせる。それはポピュリズム の隆盛に対する脅威の意識だ。
もう一度オルテガ を参照したい。彼の代表作『大衆の反逆』は正にポピュリズム の分析だった。ファシズム の足音が近づく時代、大衆文化が勢いを増す中で、それまで少数者が責任を持って引き受けてきた政治・宗教・文化のリーダーシップを大衆が侵し始めた。オルテガ はこの現象に対して厳しく批判的だ。いくつか引用してみよう(引用元はすべて中公クラシックス ・寺田和夫訳『大衆の反逆』)
大衆は、すべての差異、秀抜さ、個人的なもの、資質に恵まれたこと、選ばれたものをすべて圧殺するのである。みんなと違う人、みんなと同じように考えない人は、排除される危険にさらされている。この《みんな》が本当の《みんな》でないことは明らかである。《みんな》とは、本来大衆と、大衆から離れた特殊な少数派との複雑な統一体であった
現代の大衆的人間の心理分析表に、二つの重要な特性を書き込むことが出来る。生の欲望の、したがって、かれの性格の無制限な拡大と、かれの生活の便宜を可能にしてくれた全てのものにたいする、まったくの忘恩である。
社会生活の諸事実に注意を払いながら、この大衆的人間の心理構造を研究すれば、次のことがわかる。
(1)大衆的人間は、生は容易であり、ありあまるほど豊かであり、悲劇的な制限はないというふうに、心底から、生まれたときから感じており、従って、各平均人は自分のなかに支配と勝利 の実感をいだいている。
(2)そのことから、あるがままの自分に確信をもち、自分の道徳的・知的資質はすぐれており、完全であると考えるようになる。この自己満足から、外部の権威に対して自己を閉鎖してしまい、耳をかさず、自分の意見に疑いを持たず、他人を考慮に入れないようにする。たえず彼の内部にある支配感情に刺激されて、支配力を行使したがる。そこで、自分とその同類だけが世界に存在しているかのように行動することになるだろう。
したがって(3)慎重さも熟慮も手続きも保留もなく、いわば《直接行動》の制度によって、すべてのことに介入し、自分の凡庸な意見を押し付けようとするだろう。
これらの言葉は、恐ろしいことに本の発行から100年近く経った現代の大衆にも驚くほどあてはまる。いや、むしろインターネットの発達以降、オルテガ により描出された排他性・忘恩性・自己中心性・自己閉鎖性が世界中で加速度的に強まっているように感じる。有名人の不祥事やスキャンダルへの執拗な中傷、揶揄などは我々の身近でみられる卑近な典型例だろう。そして、大衆化・ポピュリズム 現象は当然ながら政治の中心にもおよび、その象徴は言うまでもなく第45代アメリカ合衆国大統領 ドナルド・トランプ である。
www.huffingtonpost.jp
冒頭にあげた幾つかのトピックは、ポピュリズム に抗する為に、観照派に位置する批評文化が感動派を巻き込もうした結果ではないか。世界を包み込まんとしている薄暗い脅威から身を守る為に兵を集めようとしているのではないか。そうした想いがどこか無意識的に働いてはいないか。ビヨンセ も『この世界の片隅に 』も日本語ラップ も貧困、反戦 、あるいは反差別といったテーマを共有している。「正しさ」が売りになっているのだ(それが作家の本意かどうかは置いておいて)。
そんな現象に共感を覚える部分は筆者にもある。だが、今はそれ以上に違和感が強い。数に対して数で対抗するのは手段として適切なのか。数字という見える形で勝たないと安心できないのか。それはもう一つのポピュリズム を生み出すだけではないか。
オルテガ は大衆の反語としての「貴族」、地位としてではなく責任と義務感を持った少数者としての貴族を称揚した。だが、『大衆の反逆』は大衆批判の書ではあるが、決して大衆を覚醒させんとするアジテーション の書ではなかった。なぜなら大衆に貴族観念を植え付けようとしたその瞬間に、貴族としての自負は最も堕落したポピュリズム 、つまりファシズム に転換するからだ。あくまでも個として、孤独の中で自らに課した義務を全うすること以外に人類を救う道はないと考えたところにオルテガ の慧眼はあった。大衆心理に最も精通した男の一人、秋元康 が2016年に「No!といいなよ!サイレントマジョリティ 」と少女たちに歌わせたことはとても象徴的だ。
それならば文化も、藝術も、数を価値とせず、孤独に臆することなくサイレントにマイノリティの道を進むべきではないか。少なくとも、鑑賞者として、音楽や文学を愛するものとしては、感情に溺れることなく、オートマティックな感動に踊らされることもなく、エリート的だと非難され用とも「観照派」でありたい。もちろん二つの異なる態度に橋をかけることはとても大切だし、マスとコアを行き来する重要な表現はたくさん存在する。だが、今表現に携わるものに必要とされるのは、自らが課した義務を淡々と遂行していく、いじけることも媚びることもしない自律した姿勢なのではないか。
参考→199夜『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガセット|松岡正剛の千夜千冊
ランキングは2016年に日本で発表された小説、映画、演劇、音楽アルバム、ライヴ・コンサートのなかから選んだ。順位を決めたときは上に書いたような考えをまとめていなかったけれど、1~3位あたりを見ると無意識に感じていたことなんだなと実感する。
僕の言葉がかなりの暴論を含んでいるのは承知の上だし、なるべく丁寧に書こうと心がけたが、それこそ欅坂46のそれぞれのメンバーの違いを見ずに「同質な少女たち」と決めつけてしまうような誤りもあるだろう。だが、ジャンルを貫通したときだけに見えてくる概念やイメージを素描することは批評行為を豊かにしてくれるものだし、それがひとつのところに居座れるような落ち着きを持たない(自信を持って自分のフィールドだと言える場所のない)自分のような人間が文化に貢献できる数少ないポイントだろう。なにより孤独を恐れてはいけないということは、断言と批判を恐れてはいけないということだ。
というわけで、前段が長くなったのでベストはサクッと書きます。
20.Damien Dubrovnik(12月6日原宿アストロホール )
Marching Churchとのカップリング公演だけど、今回はDamienに軍配。マイクからノイズが出るエフェクトの猥雑さと白シャツを着て髪を後ろになでつけたLoke Rahbekの高貴なビジュアルの組み合わせに息を呑んだ。2015年にLAで観た時以上の完成度。
19.ダリボル・マタニッチ/灼熱
アドリア海 に面したクロアチア の小さな村を舞台に、1991年、2001年、2011年と異なる時代の3つの恋物語 を同じ俳優が演じる。女はセルビア 人、男はクロアチア 人であることが彼らの関係に深い亀裂を生じさせている。
偶然と運命のいたずらを描くプロットや3つの話が少しずつ繋がっている感じ、音楽をストー リーの中で有効に機能させていく技術はキェシロフスキのトリコロ ール三部作や『偶然』を思い起こさせる。それぞれの話がどれもおもしろい上に力強くリンクしてくるから、観終わった後の満足感がすごかった。
18.宮沢章夫 /子どもたちは未来のように笑う(駒場 アゴ ラ劇場 9月12日)
子どもを産むことと社会との関係の今。俳優を追いつめるような最後のセリフの応酬は衝撃的だった。
http://tachesong.jugem.jp/?eid=79
17.Ryoji Ikeda (10月29日渋谷WWW-X)
こちらはMerzbow との対バン。Merzbow のノイズ金太郎飴っぷりも素晴らしかったが、Ryoji Ikeda の白黒映像とリズミカルに刻まれるノイズ音の同調は絶品だった。精神が洗われて、あたらしい視界を獲得したかのようなライヴ後の余韻。
16.堀江 敏幸/その姿の消し方
そっけない風景の絵はがきに書かれた詩のような言葉。その言葉に導かれるように「私」は詩人の孫、生前の詩人を知るもの、古物市を生業にする人々との出会いと触れ合いを重ねていく。詩人の記憶、人々の記憶、「私」の記憶がすれ違っては重なる。その記憶の重みが本書の魅力だろう。文章の短さ、軽さ、淡さがその重みをより鮮やかに浮かびあげる。
15.Fat White Family/Songs For My Mother
ブルースとガレージとクラウトロック が混ざった、酩酊感たっぷりのやさぐれロックンロールミュージック。演奏技術を一切磨かなずにぶっ飛び感だけ追求してる感じがエレガント。今年一番バンド的な魅力を放っていた存在だった。
14.滝口 悠生/死んでいない者たち
芥川賞 受賞作。最初読んだ時は醒めた目線で書いてるように感じたが、再読するとそんなことはない。思った以上にエモーショナルだ。人が縁によりつながっていることの厄介さを厄介なまま祝福したいという思い、忘れ去られてしまう記憶や感情を文章の中で残したいという思いが強く迸っている。一家 のはぐれものであり読者に忘れがたい印象を残す男、美之はまるで音楽の体をなさない記憶そのもののような音楽をインターネット上に公開する。この何気ない挿話は思いの外重要だ。すべてはつながっているという本作のテーマを凝縮しているが故に。
13.地点/かもめ(吉祥寺シアター 12月13日)
普通にやったら3時間はかかる『かもめ』を80分に凝縮しているあたりがすでに批評的。チェーホフ のメロドラマ性をとことん排除して、喜劇性をフルスロットルにしたところがすごい。
12.エド ゥアルド・ハルフォン/ポーランド のボクサー
グァテマラ出身ユダヤ 人作家の、作家自身が語り手として登場するオートフィクション的短編集。全ての短編が密接に繋がっていて、長編を手にしたかのような読後感を覚える。
「短篇小説は僕たちに見えるもの、読めるものですが、整理してみると何かそれ以上のもの、見えないけれど、それでもここに、つまり行間に、暗示的に存在する何かにもなるんです。」というのは冒頭の短編『彼方の』に登場する学生の言葉だが、この小説集全体の企図を完璧に言い表している。作家本人が語り手の、12の物語によって成された複雑なつづれおり。グァテマラとテルアビブとベオグラード とアウシュヴィッツ を280ページの中で行き来したので体全体がヘトヘトになった。
11.ブレイディみかこ /This Is Japan
彼女の文章の強さは、おそらく「自分が実際に体験したこと以外は絶対に書かない」という線引きを守れるところから来ている。この態度、言うは易く行うは難しいものの代表格で、実行するには常に常に足を動かし続けなければいけない。普通は無理。だが、彼女はしぶとさとしなやかさで泥臭くこなしていく、だからこそ、保育や経済について英国と日本の比較をする時も、どちらが優れているという話に終わらせずにそれぞれの欠点を的確に指摘できる。思うことあげたらキリがないけど、とりあえずめちゃくちゃおもしろいってことは強調しておきたいです。
10.東京デスロック/Peace(at any cost?)(3月25日キラリ富士見)
戦争、地震 や原発 などに関する様々な文書、津波 で母親を無くした少女の作文、震災時に外国から日本へ寄せられた文章、マララ・ユスフザイさんのノーベル賞 受賞スピーチ、東京五輪 召致に際して原発 はアンダーコントロール されていると全世界に言い放った首相のスピーチなどを次々と演者が朗読していく。客席とステージにはロープが張られているだけ。ロープのこちら側には喪服の女性が数人紛れ、彼女たちも立ち上がり朗読に参加する。やがて、観客の座っていた白い床がはがされ、そこからは世界中の惨状を映した写真が現れる。
会場全体が悲鳴を起こすような、世界の引き裂かれ方を具現化するような2時間。既存の言葉だけを再構築するだけで起きる大きなうねりは衝撃的だった。
9.Frank Ocean/Blonde
正直まだまだリリックなど咀嚼しきれていない部分も多々あるのだが、音像のオリジナルっぷりとポップの両立を考えるといれないわけにいかなかった。圧倒的に心地いいしな。ピッチフォークの年間ベスト2 位がこれ。他のベストに選ばれた作品、ソランジュやカニエの作品に比べても、めっちゃ変な作品。ヒップホップとインディーロック、クラブカルチャーのミックスの先達となったカニエ『My Dark Beautiful Twisted Fantasy』を『Never Mind The Bollocks』、シリアスなメッセージと豊富な音楽性が特徴のケンドリック・ラマー『To Pimp A Butterfly』を『London Calling』とするなら、『Blonde』はシーンに対する醒めた批評として機能したJoy Division 『Closer』に近い作品なのではないか。これからも聴き続けるでしょう。
8.中野成樹+フランケンズ/カラカラ天気と5人の紳士たち(STスポット横浜 12月28日)
今年一番希望を感じた作品かもしれない。別役実 が90年代に書いた戯曲が原作。『ゴトー をまちながら』的な不条理性とキャラクターの生真面目さによって生まれる笑い。「我々は死を待つことができる」という言葉は、今の時代には皮肉でもなんでもない勇気の言葉として響いた。
7.Kamasi Washington(7月24日、フジロックフェスティバル )
演奏力で一番もってかれたのがこのライヴ。メンバー全員がテクニシャンで、とくにダブルドラムはどれだけ激しいフィルを叩いた後でも一切ズレない息の合い方がすごかった。ドラムンベース 風のスピード感ある曲からゆったりとしたグルーヴのソウルナンバーまで、曲調もヴァラエティに富んでいて楽しい。優れた音楽は疲労感を吹き飛ばす。
6.Danny Brown/Atrocity Exhibition
デトロイト 出身ラッパーのサード アルバム。今までまともに聴いてなかったのを反省。Joy Division の曲名から引用したアルバムタイトル(元はJ.G.バラード の小説の名前)が示すように、ポストパン ク的な引き攣った音像と不穏なコードが特徴のトラックに独特の甲高いフロウが乗っかる。その不機嫌で攻撃的な音楽はJoy Division よりもPILの『Metal Box』を想起させる。百花繚乱の米ヒップホップ界のなかでもひときわオリジナルな存在。
5.Flight Facilities(7月22日、フジロックフェスティバル )
全ての音・メロディ・ステージ演出が踊るために機能する最高のダンス空間。適切に配置された音からは健康的な官能性が滲み出ていた。
4.山田 尚子/聲の形
橋の上の再会シーンは三回観ても泣く。映画であることに意味があるアニメ。本当に観に行って良かった。
http://tachesong.jugem.jp/?eid=102
3.アピチャッポン・ウィーラセタクン /光りの墓
2016年はアピチャッポン・ウィーラセタクン の年だった。『光りの墓』の公開に全長編映画 の特集上映、さいたまトリエンナーレ のアート展示に東京都写真美術館 の『亡霊たち』。『光りの墓』にグッときて以降、すっかり私にとっても重要な作家になった。三層の異なる時代の記憶が、二つの体のなかで一つに重なりあうロマンティックな本作は、現実に対するクリティックな視線を持ちながらも、柔らかい夢のような優しさで観る者を包み込む。
2.マイケル・ドゥドク・ドゥ・ヴィット/レッドタートル
難解さの一切ない、究極にシンプルな物語とどこをとっても美しい画面の質感。空の青さが時に応じて変化していたり、森が虫のような動きで蠢いていたり、蟹が砂浜を歩いていたり、そうしたものを眺めているときに訪れるなにか大きな歓び。世界中のどこよりも幸福な81分間があると思った。
1.木下古栗/グローバライズ
巧みすぎる描写力がどこまでもひどい内容にしか向かっていかないことに感動を覚える。だけど、ここにある嫌悪感や違和感や笑いはトランプ以降の世界のスケッチとして非常に的確。『GROBARISE』の世界を、我々は生きている。「WE ARE THE WORLD 」の意味が反転する世界を。
以上です。
ここ数ヶ月で長年逡巡していた個人的な問題から解かれたような感覚があり、それを表してみようと思った結果が今回の長めの文になったかと思います。
2016年は今まで距離をとっていた映画にがっつりと入り込むことになりまして、なんでもっと早くハマらなかったのだろうと若干後悔している最中です。
多くの人や作品に助けられた実感が年を追うごとにより強くなっている気がします。
自分が文章を書くのが、というか言葉が好きな人間だなというのが最近よくわかったので、ブログの更新頻度は高くなると思います。
だいぶ遅くなりましたが、2017年もよろしくお願いします。
VIDEO
おまけで各分野のベストのっけておきます。
アルバムベスト2 0
1.Danny Brown/Atrocity Exhibition
2.Frank Ocean/Blonde
3.Fat White Family/Songs For My Mother
4.Kaumwald/Rapa Nui Clan
5.Beyonce /Lemonade
6.宇多田ヒカル /Fantome
7.David Bowie /★
8.CtM/Suite For a Young Girl
9.Esperanza Spalding/Emily's D+Evolution/
10.Rihanna /Anti
11.Julianna Barwick/Wil
12.Paul Simon /Stranger To Stranger
13.Kanye West /Life Of The Pablo
14.Noname/Telefone
15.Anderson Paak/Malibu
16.PJ Harvey /The Hope Six Demolition Project
17.Car Seat Headrest/Teens Of Denial
18.The Novembers /Hallelujah
19.Diiv/Is The Is Are
20.Babyfather/BBF Hosted By DJ Escrow
ライヴ・コンサートベスト10
1.Flight Facilities(7月22日、フジロックフェスティバル )
2.Kamasi Washington(7月24日、フジロックフェスティバル )
3.Ryoji Ikeda (10月29日、渋谷WWW-X)
4.Damien Dubrobnik(12月6日、原宿アストロホール )
5.Aca Seca Trio(8月31日、渋谷WWW)
6.Radiohead (8月21日、サマーソニック )
7.The Novembers (11月11日、新木場スタジオコースト )
8.Christian Scott(10月30日、Blue Note Tokyo )
9.Anderson Paak(9月21日、恵比寿リキッドルーム )
10.NHK交響楽団 、オール・ガーシュイン ・プログラム(指揮:ジョン・アクセルロッド、ピアノ:山中千尋 )(8月17日東京藝術劇場)
書物 ベスト10(国内)
1.木下古栗/グローバライズ
2.ブレイディみかこ /This Is Japan
3.滝口悠生 /死んでいない者たち
4.堀江敏幸 /その姿の消し方
5.佐藤亜紀 /吸血鬼
6.青木淳 吾/学校の近くの家
7.奥泉光 /ビ・ビ・ビ・ビバップ
8.藤井光/ターミナルから荒れ地へ 「アメリカ」なき時代のアメリカ文学
9.山田詠美 /珠玉の短編
10.夏目深雪+金子遊(編)/アピチャッポン・ウィーラセタクン 光と記憶のアーティスト
書物 ベスト10(海外)
1.エド ゥアルド・ハルフォン/ポーランド のボクサー
2.ノヴァイオレット・ブラワヨ/あたらしい名前
3.エマニュエル・キャレール/リモノフ
4.アンソニー・ドーア /全ての見えない光
5.フアン・ガブリエル・バスケス /コスタグアナ秘史
6.フェルナンド・イワサキ/ペルーの異端審問
7.ジョイス・キャロル・オーツ/邪眼
8.レイナルド・アレナス /襲撃
9.ブライアン・エヴンソン/ウィンドアイ
10.アンナ・スタロビネツ/むずかしい年ごろ
映画ベスト2 0
1.マイケル・ドゥドク・ドゥ・ヴィット/レッドタートル
2.アピチャッポン・ウィーラセタクン /光りの墓
3.山田 尚子/聲の形
4.ダリボル・マタニッチ/灼熱
5.トッド・ヘインズ /キャロル
6.ジャ・ジャンク―/山河ノスタルジア
7.オタール・イオセリアーニ /皆さま、ごきげんよう
8.ジョア ン・ペドロ・ロドリゲス /鳥類学者
9.庵野秀明 /シンゴジラ
10.ルシール・アザリロヴィック/エヴォリューション
11.リチャード・リンクレイター /エヴリバディ・ウォンツ・サム
12.クリント・イーストウッド /ハドソン川の奇跡
13.深田晃司/淵に立つ
14.片淵須直/この世界の片隅に
15.ブラディ・コーベット/シークレットオブモンスター
16.イエジー・スコリモフスキ /イレブン・ミニッツ
17.バイロン ・ハワード、リッチ・ムーア/ズートピア
18.ペドロ・コスタ /ホース・マネー
19.ジャック・オーディアール /ディーパンの闘い
20.小路紘史/ケンとカズ
演劇ベスト10
1.中野成樹+フランケンズ/カラカラ天気と5人の紳士たち
2.東京デスロック/Peace(at any cost?)(キラリ富士見、3月25日)
3.地点/かもめ(吉祥寺シアター 、12月13日)
4.宮沢章夫 /子どもたちは未来のように笑う(駒場 アゴ ラ劇場 、9月11日)
5.はいばい/おとこたち(東京藝術劇場、4月2日)
6.範宙遊泳/昔々日本(東京藝術劇場、9月12日)
7.小田尚稔/是でいいのだ(新宿眼科画廊、10月12日)
8.青年団 /ニッポンサポートセンター(吉祥寺シアター 、6月29日)
9.Wけんじ /ザ・レジスタ ンス(駒場 アゴ ラ劇場、5月4日)
10.青年団 リンク ホエイ/麦とクシャミ(駒場 アゴ ラ劇場、8月14日)