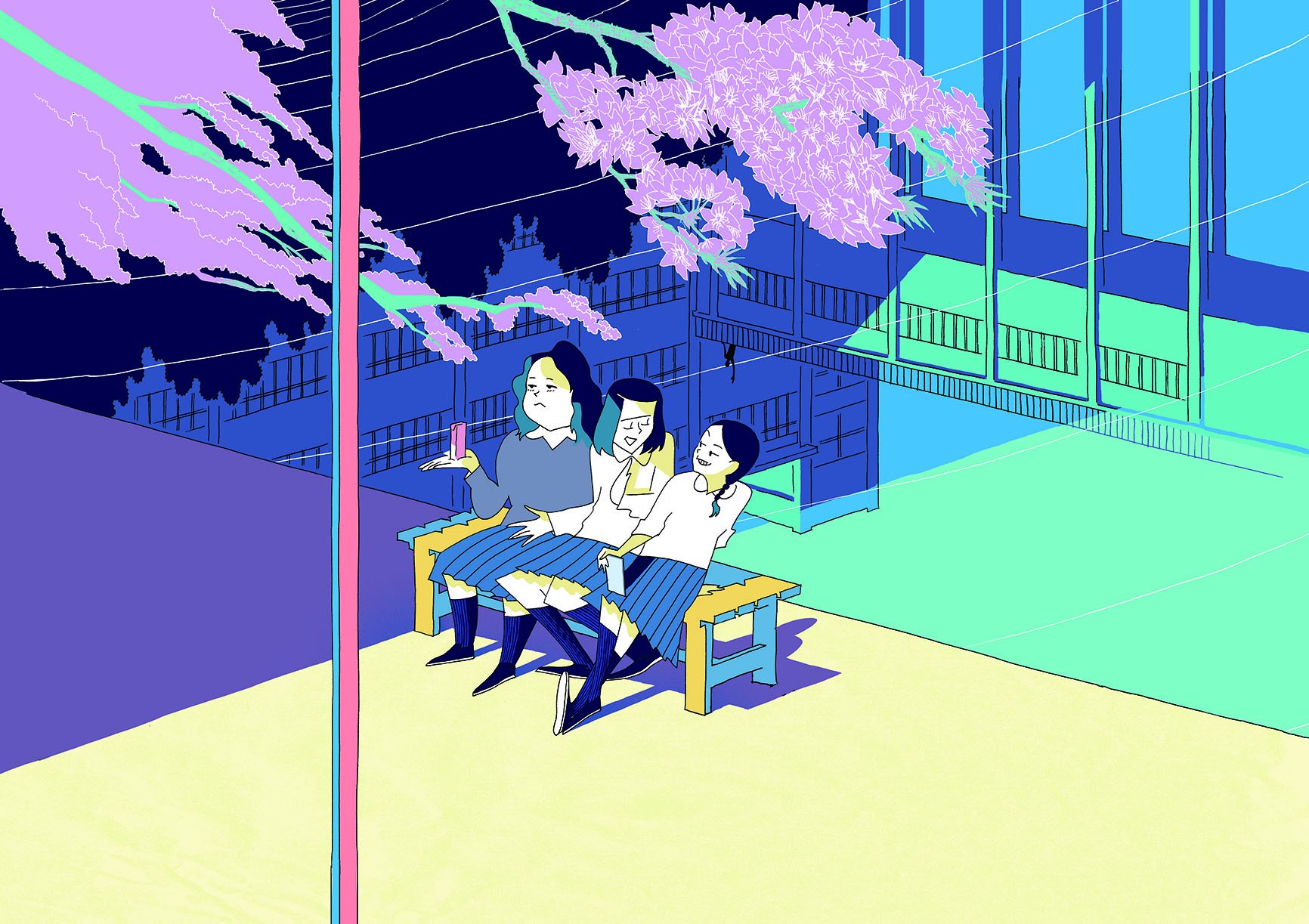はじめての海外文学、何を読めばいいのかーーこんな風に問われたら今なら僕はこの一冊を勧める。

フリードリッヒ・デュレンマット(1921〜1990)はスイス生まれのドイツ語劇作家・小説家であり、この素っ頓狂なタイトルの小説は1954年に発表された。デュレンマットの作品を読むと、こんなおもしろくてヨーロッパで知名度が高い(らしい)作家が日本で知られていないことがとても不思議に思えてくる。
まず言えることは、この作家はスイスと聞いて連想されるような朗らかな自然のイメージ、要するに「アルプスの少女ハイジ」のイメージからかけ離れたスイスの姿を提示するということだ。本作の舞台は雨が降り続ける陰鬱な冬の街である。やりきれない天気が続くなかで、主人公の中年男アルヒロコスが姿を現す。この男はいつもメガネをかけていて、40歳を過ぎても女性経験がなく、道徳意識が強く、尊敬すべき人間に順位をつけている(1位は大統領、2位はキリスト教の司教、3位は彼が勤める機械工場の社長だ)。糞真面目な変人である。彼がよく通うバー(元プロ自転車選手がマスター)のおかみさんは身寄りがいないことを心配して、新聞に結婚相手募集の広告を出すよう説得する。広告の見出しとしてアルヒロコスが提案したのが本作のタイトル、「ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む」だ。彼は先祖がギリシア人だったと言い張るのである。
広告を出すや否や、彼に会いたいという女性が現れる。待ち合わせのバーにやってきたのはなんと気品に満ちた美しい貴婦人。彼女と出会った瞬間から男の運勢は急に好転する。デートをすれば尊敬する大統領や司教が彼に挨拶をするし、職場に行けば下っ端社員でしかなかったのに急に昇進の話が持ち上がる。思わぬ幸運の連続に戸惑いを隠せないアルヒロコス。しだいにその幸福が、彼を追いつめていく。
本作にはカフカの諸作を思わせる不条理な展開が待ち受けている。だが、カフカが不条理な不幸(虫に変身したり、覚えのない罪でさばかれたり)を扱ったのに対し、デュレンマットは不条理な幸福を扱っており、その幸福が人の生を困難なものに変えていく様を描いているのだ。
おもしろいのは、何故やってきたのかわからないと思われた幸せに、実は確かな理由があったことが示されているところで、謎が謎のまま残されているわけではないのだ。そして、この理由が主人公を苦しみのどん底へと陥れるが、美女と会った時点で彼の運命は決まっていたことが後になってわかる。
デュレンマットは運命に拘る作家だ。どうあがいても変えられない宿命を自覚したとき、人はどう生きるべきかというテーマが彼のいくつかの作品に共通している。たとえば『デュレンマット戯曲集 第一巻』(https://www.choeisha.com/pub/books/53543.html)に収められた『ロムルス大帝』、は西ローマ帝国最後の皇帝が滅亡を免れない帝国の代表者として自らの定めと向き合う様子を書いた、正に運命についての作品である。こうした作品群を読むと、ぼくは批評家佐々木敦が書いた「マジ」な自己啓発本『未知との遭遇』を連想する。
未知との遭遇【完全版】 (星海社新書) | 佐々木 敦 |本 | 通販 | Amazon
この本は選択肢のあまりの多さと「あの時こうすればよかったのに…」という後悔に苛まれやすいインターネット時代の現代人の特色を素描しながら、古谷実、本谷有希子などの作品を援用しつつ、「起きたことはすべていいこと」と考える「最強の運命論」を説いた一冊である。佐々木がデイヴィッド・ルイスや入不二基義の議論を参照しながら「全ては決まっているが、人間は有限な存在であり未来について何も知ることはできない。だからこそ、人は未知に驚くことができる」という内容のことを語る時、彼はデュレンマットについて語っているのではないかと思わず錯覚する。このスイス人作家の著作には運命、あるいはどうしようもない限界を自覚しつつ未知のものに驚くためのヒントが、いくつも眠っているのだ。