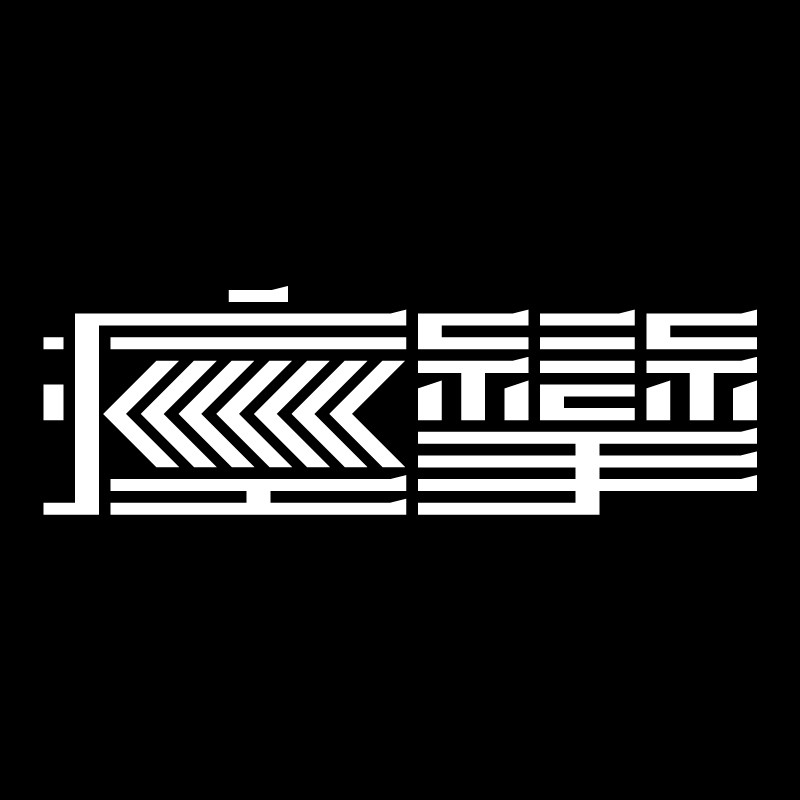
李氏くんがほぼ一人で編集した音楽批評誌『痙攣』が先日発売されました(そして早速売り切れ!現在増刷対応中とのことです、偉い)
僕もこちらに『THE NOVEMBERSと変革の最低条件』という論考を寄せました。
昨日うちに届いて、勢いで午前中に全部読み終わったので、勢いで全記事のレビューでもしてみようかと思い立ちました。どうやら僕は参加者の中で比較的年長者らしいので、「口うるさい兄」役を演じてみます。とはいえ批判は抑えめにするつもりですが。
あまり時間もないのでどんどんいきます。
0.序文(李氏)
ちょっと強引かつ硬い感じもしますが、「ポップ・ミュージックは今後個人史への解体と正史への欲望に大きく分断されるが、人間の生理は普遍的であり、その生理(ここでは「チル」と「暴力」との振り子運動)に着目することで個人性と集団性をつないでいく」という論旨は良いものを含んでいる。何が良いというと、人間生理を「チル」と「暴力」で考えているところ。当然それは暴論だが、「音(楽)と人間の関係性」という全ての音楽関係者(広く解釈すれば全ての人間)に関わるテーマを提出できているかもと思った。
1.小沢健二、ジョーカー、BUCK-TICK -生活から生へ-(李氏)
気概は伝わってくる。しかし構成に問題が多い。まず、小沢健二、ジョーカー、BUCK-TICKという三題噺を串刺しにするテーマやワードが実は提示できていない。オザケンとジョーカーはNYで繋がるが、BUCK-TICKは繋がらない。オザケンとBUCK-TICKは1995年で繋がるが、ジョーカーは繋がらない。ジョーカーとBUCK-TICKは「弱い人間像と疾走のモチーフ」で繋がるが、オザケンは関係ない。3人の登場人物が一堂に会するフィールドが、用意されていないのだ。また、「疾走」というモチーフは実はBUCK-TICKに関して明記されていない。辛うじて楽曲を形容するときに「疾走感」という言葉が使用されるが、ロックバンドに「疾走感」のある曲なんて星の数ほどあるのであって、BUCK-TICKの特異性として認めがたい。むしろ「全力疾走」してきたと歌う小沢健二の方が「疾走」というモチーフを取り出しやすいのではないか。
『ジョーカー』の読解もかなり不満。映画後半の暴動シーンについて「闘争し逃走するその祝祭性」と李くんは書いているが、あのシーンに出てくる群衆の誰が「闘争」し「逃走」しているのだろう。「逃走」しているのはむしろ暴動から逃げ惑うウェイン一家じゃないか。僕には被害者という仮面を被ったポピュリストと、扇動に乗じて破壊に興じる輩の群れとしか感じられない。あの映画は、そうした構図をアイロニーとして描いている(ことが最後の病院のシーンで示される)ところにギリギリ良さがあるはずだが(個人的に好きな作品ではないけど)。
・・・細かくあげるとキリがないのだが、乱暴にまとめると「面白い批評文は基本的に論理とテーマの一貫性を保っている」ということが言いたいのです。書きたいテーマが沢山在る事はそれだけで才能なので、上記の点を意識しながら書き続けて欲しいと思います。
あと、李くんが今回書いている文章ってほぼ全て「相反するAとBがあって、そのどちらにも与しないCがある」という弁証法を思わせる構成になっていて、他の構成の文章も読んでみたいな(あるいはもっと洗練された弁証法を読んでみたい)。
BUCK-TICKのサウンドと歌詞のつながりから「個人の悲劇」と「集団の悲劇」を描くところは可能性感じました。とはいえ、BUCK-TICKは言葉の意味性だけ抜き出すと陳腐になるな・・・
2.次世代の「ロック」の在るべき姿-Bring Me The Horizon『Amo』論-(カヤマ)
「ロックスター」の変化というテーマは興味深いし、今までちゃんと聴いてなかったBMTHも聴きたくなりました(今日聴いてた)。ただ、カヤマさんが新しい「ロック」の定義として挙げている「センセーショナルなファッション」「他のジャンルやポップシーンへの興味」「停滞の拒否」「悲痛や孤独の表現」って全て今までのロックに当てはまっているというか、むしろ60年代から続く「ロック」の基本命題ではないでしょうか。ビートルズもディランもボウイもクイーンもニルヴァーナもそういった人たちでしょう。今の「ロックスター」の新規性はもっと別のところにあるのでは、というのが僕の感想です。ロックに対する先行言説は押さえておくと役立ちます。
加えて、「未来への希望」「新しい夜明け」「無限の進化の可能性」という文は紋切り型に過ぎるので、もっと読者に引っかかる言葉選びを考えた方が良いです。
3.世代と環境を巡って(清家、李氏対談)
インタルード的な短い対談だけど、人の音楽遍歴が知れるのは面白いですね。
4.モンタージュ音楽論-Solange、小袋成彬、JPEGMAFIA-(♨︎)
ツイッターでも「コラージュ」の定義を巡って議論めいたことになっていたけど、この文章を読む限り♨︎さんが示している見解が混乱の元だと感じる。おそらく♨︎さんは最近の音楽の「断片性」を指して「コラージュ」と言いたいのだろうけど、ここで提示されている例は「コラージュ」とは認め難い。小さい断片をあまた集めて、本来とは別のあり方で繋げ合わせる手法が、美術用語として広がった「コラージュ」の大まかな定義であり、つまり「断片から全体を形成する」のがコラージュである。その一方、Solangeが新作のインタビューで「15分の演奏の中からベストの3分を探すようにした」と語ったエピソードが論考で紹介されているが、つまり本稿で描かれているのは「全体から断片を抜き出す」方法であって、コラージュの手法とは逆立している。むしろこれは「断片化(英語ならFragmentationかな)」とでもいうべき特徴だろう。作品を抽象化する際には細心の分析が必要だし、言葉の扱いにも慎重であるべき。もっと魅力的に議論を展開できたと感じる。惜しい。
言葉の扱いでいうと、モンタージュとコラージュを混ぜて使っているのも良くない。というのは、「コラージュ」がもともと絵画に関する用語で、「モンタージュ」は映画の用語だから、そこには全く異なる歴史的文脈が含まれている。絵画と映画(そして音楽)の構造や歴史性の違いを描きつつ、用語の差異を導き出さない限り、こうした言葉の並列は余計な不明瞭を招きかねない。キーとなる言葉を一つに限定した方が議論がクリアだったと思われる。ただ、扱われてる素材は面白く、広がりのある話だった(だからこそTLで話題になったんだろうし)。
5.もっとチルしていたいのに(ヨアケノ×吸い雲対談)
これは面白かった。Aphex Twinの初期のローファイな微細ノイズにラジオ性を見出し、そこから10ccとlo-fi Hip Hopに繋がるのは意外性もありかつ納得感もあり、一つの魅力的な「ローファイ史」を描き出せる予感を覚えた。良いノリが出てて、学びも多かったです。
6.Vegyn『Only Diamond Cut Diamonds』レビュー(吸い雲)
吸い雲さんの文が良いのは先行文献を意識しているところで、「今までの人はこういってるけど本当はこうでしょう(orこういう可能性もあるでしょう)」という書き方になっている。面白いレビューは文章に含まれない情報を多数抱え込んでいるもので、だからこそVegynと、あまり繋がりを指摘されてこなかったダブステップの雄Skreamとの連続性を描くことができる。聴取体験を文に含まれているのも良いですね。少し無難な印象はあるけど。
7.長谷川白紙『エアにに』(李氏)
だんだん疲れてきた。李くんの文章について先ほど長く書いたので軽くの言及にとどめます。正しいかどうかはさておき、「発散」だけにフォーカスした方が面白かった気がする。
8.Metal The New Chapterの可能性(s.h.i、清家、カヤマ対談)
メタルは僕が疎いジャンルなので単純に沢山の固有名とその関係性を知ることができて勉強になりました。面白かったです。ただ、Jazz The New Chapterをなぞるだけの議論になった印象はある。JTNCに対する批評性があればもっと良かった。
9.NINE INCH NAILS(not equal)Trent Reznor(李氏)
カニエとクイーンの例が強引すぎて不器用な弁証法になっていると感じた。トレントにフォーカスしても良かったのでは?
10.THE NOVEMBERSと変革の最低条件(伏見 瞬)
わたしの文章です。付け加えるコメントはあまりありませんが、インダストリアルと2010年代の関係性をもっと考えた方が良かったなとさっき思いました。文のリズムにも改善の余地あり。
11.戴冠 -ビリー・アイリッシュと私-(清家)
個人的なベストはこちら。ユリイカのビリー・アイリッシュ特集のどの文章よりも良かった。「戴冠」というワードセンスがまず素晴らしい。彼女の強みと、背負ったものの重みを一単語で見事に表現している。この言葉が出てきただけで勝ち。女性と男性との不均衡をテーマにしつつ、そこに自らの体験とビリー・アイリッシュ解釈が無理なく結びついている。読解が歌詞によりすぎではという疑問もよぎるが、今回はこれで良かったんだと思う。細密な分析による納得も豊富な知識による位置付けの確かさも薄いが、文章力一本でねじ伏せた感じ。「音楽業界に足を踏み入れ、肌感覚で呑み下さざるを得ない「構造」を悟った。」とか「鈍色の瞳は私たちの感傷の道具なんかじゃない」とか、いちいち文にキレがある。
12.「叫ぶ女」(s.h.i)
Roadburn Festivalという存在を恥ずかしながら存じ上げなかったし、そこで行われるキュレーションシステムやメタルにおけるジェンダーの格闘も当然知らなかった(THE BODYやLingua Ignotaは好きです)。大変勉強になりました。
前述したユリイカのビリー・アイリッシュ特集でs.h.iさんが作った「声量から声質へ」というテーゼ、全然ピンときてなかったのだけど、メタルが背景にあることを知って初めて納得した。
13.声と革命-GEZAN『KLUE』論-(李氏)
どうしても李くんの論考には厳しめになってしまうんだけど、こちらも「革命」の具体的様相に触れようとしながら、最後はどうにも非実体的な結論に陥った感は否めない。まぁ左翼的な革命論自体がおしなべて非実体的なのかもしれないが。
編集後記(李氏)
厳しいコメントも多くなったけど、李くんは自分で発案して、一人で編集して、発送作業も一人でやって(これが地味にキツい!)、短期間で実行に移したのでマジで偉いと思います。僕も刺激を受けました。
これを継続して、いろいろ修正しながら良き本を作っていくのが大切です。前提条件として、質の高い文章が並ぶ必要があるので、ちょっと「おせっかい」してみたくなりました。Twitterとの関係性とか男女の不均衡とか色々考えなくてはいけないトピックは多いだろうが、まず率直に、まだまだ論の程度が低い。俺を含めたみんな、もっと切磋しなさい。




